院生の就活事情について ~学部生との違いは?~
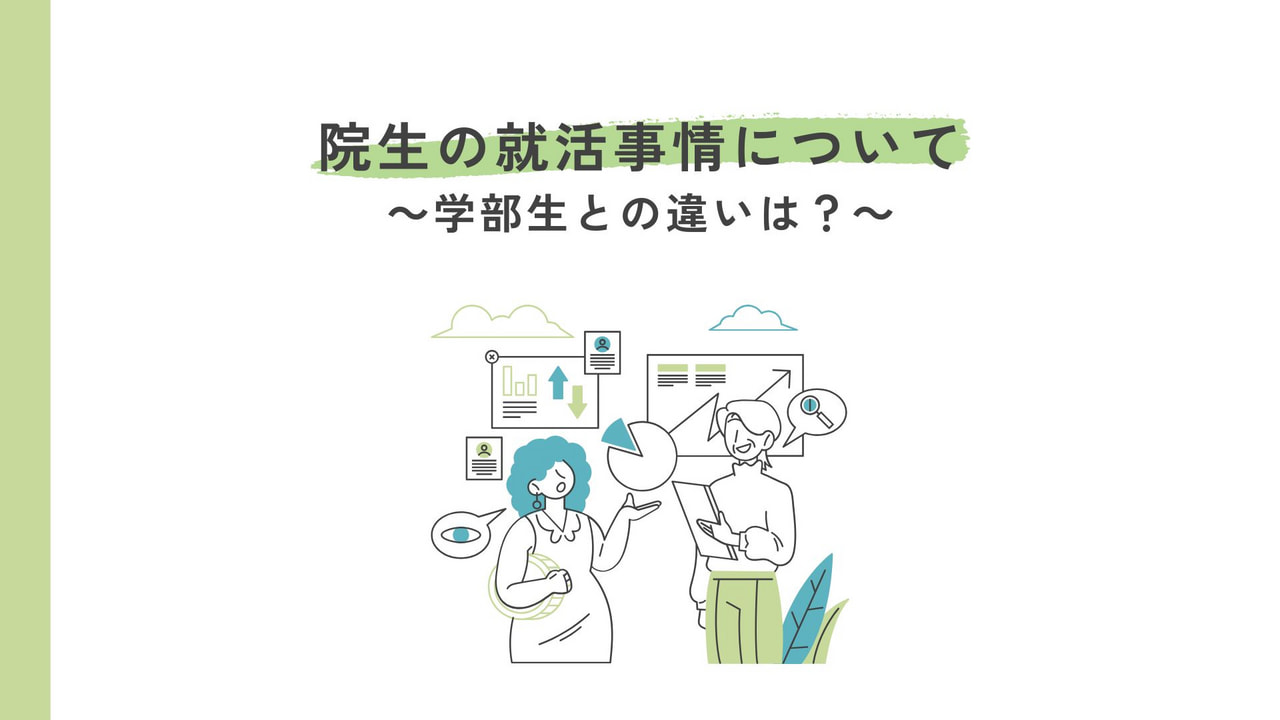
学部生の就活は情報がたくさん公開されているけれど、院生の就活情報はあまり耳にすることが少ないのではないのでしょうか。今回はそんな院生ならではの就活事情やポイントについて紹介します。
【院生の就活】
院生共通の悩みとして上げられるのが「研究との両立」があります。進学してすぐの修士1年目の夏にはインターンシップがあるため、研究を新しく始めてすぐに就活を始めなければいけません。また、学会に参加する院生は、準備と並行して就活を行っていることもあります。このような状況から、時間を効率的に使い、就活と研究を両立させることが必要になってきます。
【院生と学部生】
院生は就活において「有利」になったり逆に「不利」になるのかというのは、院生だからと言って有利ということはあまりないと言われています。院生か学部生かというよりも、新卒の採用においては、人柄とポテンシャルが評価されるのが通例であるので、専門的なスキルを求めているということが少ない傾向にあります。ただし、理系技術職の場合などは実験などで培った専門的なスキルが求められることも多く、院生という括りで全体を見渡すと、有利になる場合も不利になる場合もあるため、総合で見るとゼロに近くなります。では、どういった場合に「有利」になり、どういった場合に「不利」になるのかについて説明していきます。
<有利になる場合>
院生が有利になる場は、研究をメインに行っているため、論理的な思考力が鍛えられている場合が多いです。研究背景を踏まえ、仮説を立て、検証し、考察を行う、そして考察からさらに仮説を立て検証していくというサイクルを繰り返すため、意識せずとも学部生に比べると論理的な考え方が身についている可能性が高くなる傾向にあります。なので、そこの評価が高くなる傾向があると考えられます。
<不利になる場合>
不利になる場合は、「院生だから」という理由で期待値が高く設定されていることも中にはあります。院生は論理的な思考力が武器になると同時にそこが前提で考えられてしまうことがあります。なので、ある程度期待をされている分、基準が高くなっていることも考えられます。
【院生がアピールできるところ】
<なぜ大学院に進学したのか/大学院で何を得たのか>
院生がアピールできるポイントの1つとして、「大学院に進んだ理由」や「大学院で得たこと・考え方」を論理的に示すことがあります。現在は理系技術職以外はポテンシャル採用という採用方法がされていることが多くあります。なので、採用担当者は学生の「人柄」「ポテンシャル」を知りたいという傾向にあるためです。
修士の学生の場合、まずは2年間で何を得ることが出来たのかを考え、そこに至るまでの過程を深堀していきましょう。
【まとめ】
院生の就活に関する事情が少しでもつかめましたでしょうか?
基本的に新卒採用の場で、院生と学部生の違いはないものと考えてよいでしょう。ですが、学部生よりも数年多くの研究をして知識を深めたことは事実です。なので、知識を深めたプロセスや理由についてしっかり考えて伝えられるようにしておきましょう。
 ナジック
ナジック