文系学生と理系学生の就活の違いについて解説!
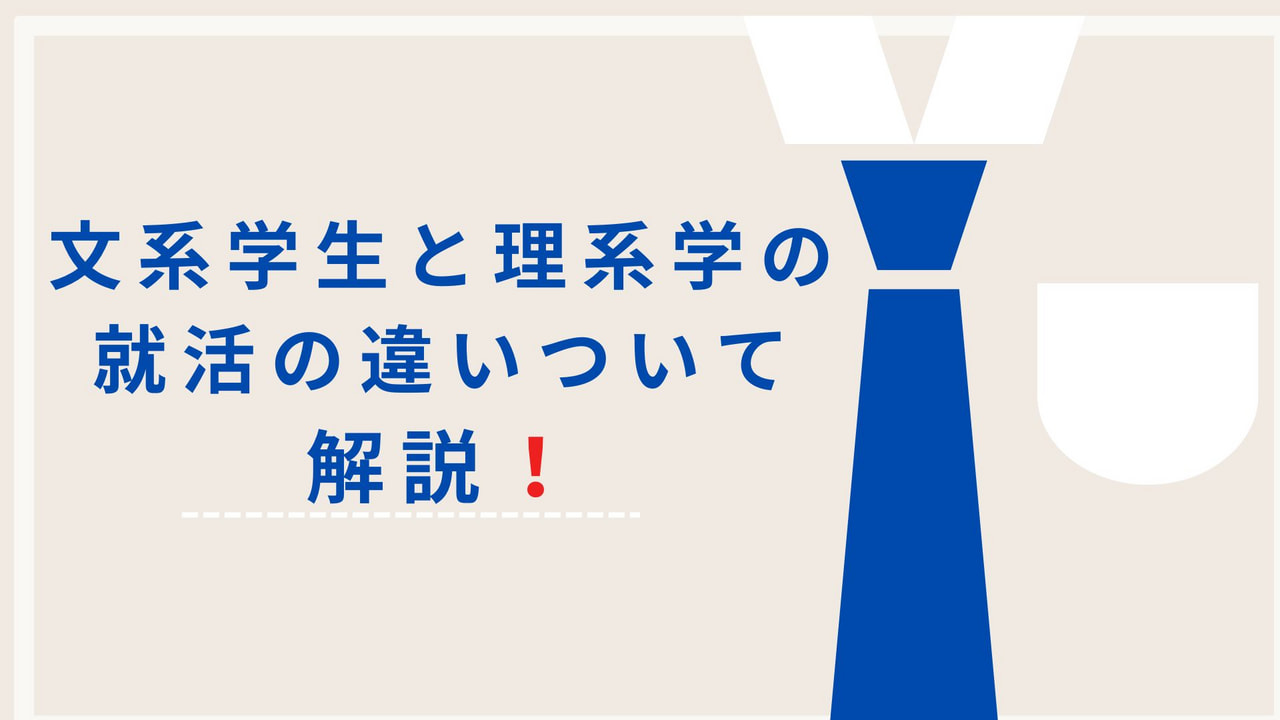
文系と理系の就活には、色々違いがあるということを知っていましたでしょうか。今回はそんな文系と理系の就活に見られる違いについて解説をしていきます。
【大量にエントリーをして長期的に就活をする文系、少数エントリーで短期間で終わらせる理系】
文系の就活の特徴として見られるのが、10社20社など多くの企業にエントリーをする傾向にあります。人によって個人差がありますが、エントリー数が多い分内定率が高いというわけではないので就活の期間を「長期間する」という認識の人が多いです。理系の就活生も、研究の合間の時間で就活をしなければいけないので大変ですが、エントリー数は比較的少なくても、短期間で大企業の内定を獲得できるケースが多いです。
【理系と文系の就活の違いはどの要因から生まれている?】
前述でも述べたように文系就活生と理系就活生では就活に違いが見られます。このような違いがどのように出てくるのかについてご紹介していきます。
<アピールできるスキルの違い>
まず、最も大きな要因として考えられるのは、企業にアピールできるスキルの差です。
文系の学部生は一部の専門職に進んだ人を除いて、基本的には学部で学んだ学問とはそれほど関係のない会社に入社をすることが多いです。このように文系学部は学んだ学問を就活にあまり活かさず、「コミュニケーション能力」や「仕事に対する熱意」などの将来の資質の部分をアピールしています。しかし、理系学生は学部や大学院で学んだ学問をそのまま就活に活かすことが出来ます。企業にとってはどの学生の研究が今後の会社の発展にどのように貢献してくれそうかを判断しやすく、学制側から見てもそれだけ他の就活生との差別化が容易になります。
<面接コースの違い>
企業にアピールできる要素に違いがあると、内定までのコースにも差が出てきます。
文系の学生は将来性のある人材なのかどうか、企業とマッチするのか、どのように貢献してくれるのかという部分が一回の面接では判断することが出来ません。そのため、毎回面接官を変えながら複数回の面接を行い、様々な角度からの人間性のチェックを行う必要が出てきます。なので、ほとんどの企業では、文系採用は最低でも3回以上の面接を行う傾向があります。
一方で理系学生は、面接回数が少なく、推薦も使うことができます。自身の取り組んだ研究と関係のない業界は受けにくいというデメリットはありますが、その分企業にとっても魅力的な技術を有しているため、内定までの面接の回数は1~2回で済みます。また、自由応募以外にも推薦制度を利用することで100%とはいかないですが、内定を獲得する確率を飛躍的に向上させることが可能となります。
<採用職種の違い>
文系と理系は、入社後の職種も全く違います。
文系学生は、会社の「経営」に携わることを期待されていることが多いです。なので、事務系の採用コースから入社した場合には、どの会社でも半数以上の新入社員は経営の根幹をなす営業部門に配属されるケースが多いです。それ以外には、人事、法務、経理、総務など会社経営を円滑に進めるバックグラウンドの部門に配属されます。
一方で理系学生は、会社の「生産」の役割を担うことが多いです。そのため、研究所で基幹研究や新商品の開発に携わる研究開発や、工場での生産を最適化させる生産管理などの職種に配属されることが多いです。
【まとめ】
このように文系学生と理系学生では、就活に様々な違いがあります。ですが、志望企業の理解や自身の強みをわかりやすくアピールする能力はどの就活生にも必要とされます。自己分析・業界研究・企業研究はしっかりと行い、準備をすることが必要です。
 ナジック
ナジック